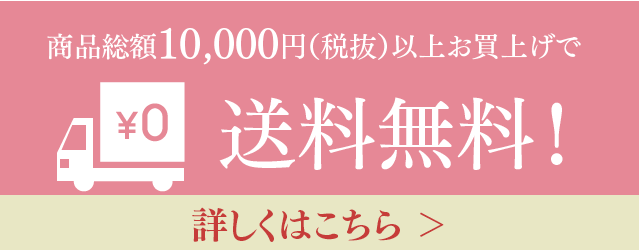お店案内
有限会社 昇久堂
社名: 有限会社 昇久堂
住所:
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺5丁目26-27
電話: 096-381-4583
FAX: 096-381-2069
メール:info@shokyudo.jp
ホームページ:https://www.shokyudo.jp
業務: 医薬品の販売及び配置薬販売
許認可・資格:
登録番号T4330002005200
熊本市 医薬品販売業許可 第 345号
店舗販売業
店舗管理者 小田 朱美
登録販売者 小田 正博
医薬品販売担当
登録販売者 小田 正博
登録販売者 小田 朱美
代表取締役:小田 正博
営 業 部 長:福島 三郎
店舗営業時間:
月曜~金曜 午前9時~午後5時
FAX・インターネット受付:24時間
お客様相談窓口:
昇久堂 096-381-4583
平日 午前9時~午後5時
時間外はホームページのお問い合わせフォームより、お願い致します。
第1.店舗の管理及び運営に関する事項
1.許可の区分の別
店舗販売業
2.販売業者の氏名又は名称その他の販売業の許可証の記載事項
・氏名
有限会社 昇久堂
・店舗の名称
有限会社 昇久堂
・店舗の所在地
熊本県熊本市中央区水前寺5丁目26-27
・許可番号
熊本市 医薬品販売業許可 第345号
・発行年月日
平成31年1月28日
・有効期限
令和7年2月4日 から 令和13年2月3日 まで
3.店舗管理者の氏名
小田 朱美
4.当該薬局に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名及び担当業務
店舗販売業
店舗管理者 小田 朱美
登録販売者 小田 正博
医薬品販売担当
登録販売者 小田 正博
登録販売者 小田 朱美
代表取締役:小田 正博
営業部長:福島 三郎
5.取り扱う一般用医薬品の区分
指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
6.当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者は「登録販売者 氏名」の名札に白衣
7.店舗営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間
実店舗開店時間:
月曜~金曜 午前9時~午後5時
特定販売を行う時間:
月曜~金曜 午前9時~午後5時
営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間:
月曜~金曜 午後5時~翌午前9時
土曜・日曜・祝日 24時間
8.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
電話:096-381-4583
第2.特定販売届出書の記載事項
1.実店舗の主要な外観の写真
ページ下部に掲載
2.一般用医薬品陳列状況の確認できる写真
ページ下部に掲載
3.現在勤務している薬剤師または登録販売者の表示
登録販売者 小田 正博
登録販売者 小田 朱美
4.一般用医薬品の使用期限に関する解説
使用期限まで180日間以上ある医薬品を発送します。
・許可番号及び年月日
許可番号:第345号
年月日:令和7年2月4日 から 令和13年2月3日 まで
・店舗の名称
有限会社 昇久堂
・店舗所在地
熊本県熊本市中央区水前寺5丁目26-27
・販売方法の概要
広告方法:通販サイト
配送方法:宅配便
・届出年月日
令和7年4月30日
・届出先
熊本市
第3.一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
1.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品:一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品、毒性もしくは劇性が強い医薬品
第一類医薬品:一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分または一般用医薬品として特にリスクの高いと考えられる成分を含む医薬品
第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来たす健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品
※指定第二類医薬品は第二類医薬品のうち特に注意を要するもの
第三類医薬品:日常生活に支障を来たす程度ではないが身体の変調、不調が起こる可能性のある成分を含む医薬品
2.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
医薬品パッケージ(外箱・外装)および添付文書にリスク区分を表示します。表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。
1.要指導医薬品は、要指導医薬品と表示します。
2.第1類医薬品は、第1類医薬品と表示します。
3.指定第2類医薬品は、第②類医薬品(四角枠囲み付)または第②類医薬品と表示します。
4.第2類医薬品は、第2類医薬品と表示します。
5.第3類医薬品は、第3類医薬品と表示します。
3.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
医薬品の情報提供は、専門家が行う。
1.要指導医薬品…薬剤師が対面で文書を用いて情報提供する(義務)
2.第1類医薬品…薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)
3.第2類医薬品…薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)
※指定第2類医薬品の購入時は禁忌の確認を行い、薬剤師、登録販売者に相談してください。
4.第3類医薬品…義務はないが専門家が情報提供に努める
4.医薬品の陳列等に関する解説
【実店舗での陳列について】
リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時の販売はできません)
1.リスク別陳列
・同じ薬効(例えば胃腸薬や目薬など)群でもリスクが混在しないように、リスクごとに集合させた陳列を行います。
2.指定第2類医薬品・第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
・許可を受けた医薬品売り場に陳列します。尚指定第2類医薬品に関しましては、情報提供カウンターから7m以内に陳列します。
【薬局における医薬品の管理】
保管管理
医薬品棚等への陳列
○要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列等
・薬局においては、 医薬品を医薬部外品等の他のものと区別して陳列する。
・医薬品の陳列は、 要指導医薬品及び第1類医薬品、第2類医薬品又は第3 類医薬品の区分ごとに混在させないように陳列する。
○要指導医薬品及び第1類医薬品の陳列等
・ 要指導医薬品及び第1類医薬品は要指導医薬品及び第1類医薬品陳列区画内又は購入者等が手の触れられない場所もしくは、 鍵のかかる設備に陳列する。 なお、 施錠設備の場合には、 薬局管理者等の薬剤師が鍵を管理する。
※ 要指導医薬品及び第1類医薬品を情報提供設備 (カウンター)の背面(バックザカウンター) の棚に陳列する場合は、購入者等が直接手に触れることができないよう、 パーティション等により物理的に遮断され、 進入する ことができない措置が講じられた設備に陳列する。
※ 同一又は類似の薬効の第2類医薬品等を陳列している場所において、 要指導医薬品及び第1類医薬品を陳列したい場合は、当該製品情報 (製品名リスト、製品カード等) や空箱等製品の入っていないものを陳列する。また、外箱によって当該製品情報を示す場合には、購入者等が外箱であること、及び、薬剤師による情報提供を受けた上で購入するものである旨を当該容 器に表示する。
○指定第2類医薬品の陳列等
・指定第2類医薬品は情報提供設備 (カウンター)から7m以内の範囲に陳列するか、 第1類医薬品陳列区画内又は購入者等が手の触れられない場所もしくは、 鍵のかかる設備に陳列する。なお、施錠設備の場合には、薬剤師が鍵を管理する。
【第一類医薬品の陳列方法の詳細】
購入者が直接手に取れない場所への陳列:
第一類医薬品は、購入者が自由に手に取って閲覧できないように、カウンター内でカウンターから1.2m以上離れた場所に陳列するか、鍵のかかった設備に陳列する必要があります。
薬剤師の関与:
第一類医薬品は、薬剤師が情報提供を行い、 購入者が適切な選択と購入ができるように、 販売側のみが手にとれる方法(オーバー・ ザ・カウンター) で陳列することが望ましいです。
陳列場所:
要指導医薬品及び第一類医薬品は、陳列区画 の内部または近接する場所に設置する必要があります。
情報提供場所:
情報提供場所は、陳列区画の内部または近接している場所に必要です。
その他:
第一類医薬品を陳列する際は、 製品を直接購 入者が手の届かない場所に配置し、薬剤師・ 登録販売者の物理的な管理ができる場所に陳列することが推奨されます。 また、店頭に複 数個置かない、 商品カードや空箱での対応、 製品に目印をつけるなどの管理も必要です。
【要指導医薬品の陳列に関する主なルール】
混在禁止:
要指導医薬品と一般用医薬品は、混在しないように陳列する必要があります。
陳列場所:
・ 要指導医薬品陳列区画を設ける必要があります.。
・ 陳列設備は、要指導医薬品列区画内または近接する場所に設置します。
・ カウンター内で陳列する場合は、カウンターから1.2メートル以上離す必要があります。
・ 鍵をかけた陳列設備に陳列することも可能です。
購入者が触れないように:
・ 購入者が直接手に取れないように、鍵をかけた陳列設備に陳列するか、1.2メートル以上の距離を保つなどの措置が必要です.
5.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9425(有料)をご利用ください。(平日09:00~17:00)
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものを含みます)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが医薬品副作用被害救済制度です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
6.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【医薬品副作用被害救済制度】
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、医薬品副作用被害救済制度です。
【相談受付窓口】電話: 0120-149-931 受付時間:午前9:00~午後5:00(月~金 祝日・年末年始を除く)
7.個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
当サイトのプライバシー規約に従い適切に取り扱います。
8.その他必要な事項
医薬品を適正にご使用いただけない可能性がある場合の措置
お客様の購入状況等から、適正にご使用いただけない可能性があると登録販売者が判断した場合は、注文キャンセルまたは配送停止の措置をとらせていただく場合がございます。